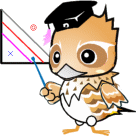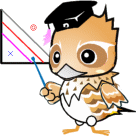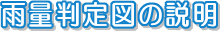 |
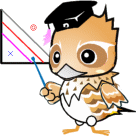 |
 |
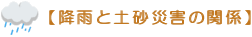 |
土石流や崖崩れなどの土砂災害は、地表に降った雨が地下に浸透し、地盤内部の結合力を弱めるために発生すると考えられています。
従って、さほど大雨でなくても土石流が発生する場合もあれば、大雨が降っても土砂災害には至らない場合もあります。地盤がたっぷり水を含んでいる場合は少ない降雨でも注意する必要があります。 |
|
 |
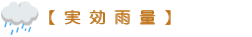 |
土石流の注意状態を把握するために、現在より前に降っていた雨量(地盤に浸透した雨の量)を計算して使います。これは経過時間によって減少します。
この雨量と現在降っている雨の合計を「実効雨量」といいます。 |
|
 |
 |
土石流注意1、注意2は、「実効雨量」により判定します。
◎現在の降雨状況が注意1や注意2のラインを超えたとき、土石流注意のお知らせをします。 |
<判定図 例>
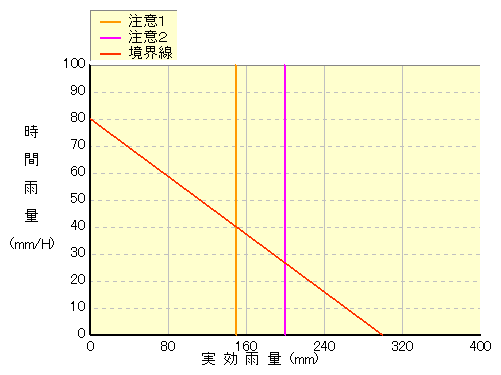 |
|
 |
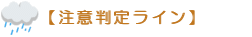 |
注意1,2の判定ラインは、過去に土石流が発生したときの降雨と、発生しなかったときの降雨をグラフにプロットして決めています。 |
| 1: |
過去の降雨(災害が発生した降雨◎、しなかった降雨×)をグラフにプロットします。 |
 |
| 2: |
危険な領域と安全な領域に分ける境界線を引きます。 |
 |
| 3: |
境界線を補助線とし、危険な領域に達する手前に注意するためのラインを引きます。実効雨量がこれを超えたら「注意1」「注意2」をお知らせします。 |
 |
| |
「注意1」 土石流災害の発生に注意して下さい。 |
| 「注意2」 土石流災害発生の可能性が高くなっています。 |
| |
| 4: |
「注意1」「注意2」の基準は目安ですので、雨量情報一覧や気象台発表の気象情報と併せてご利用下さい。 |
|
|
 |
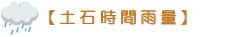 |
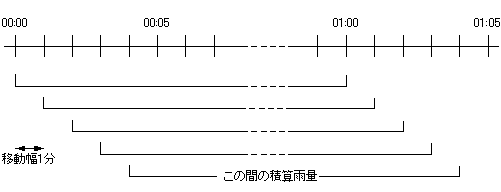 |
<時間雨量>
1時間の積算雨量、つまり1時間前から現在までの降雨量で、上記の様に1分ごとに算出しています。なお、1時間雨量を時間雨量と称する場合もあります。 |
|